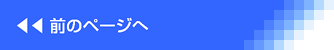 |
 |
 |
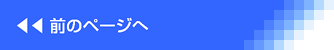 |
 |
 |
 |
■50000系(1994年) 大阪難波と関西空港を結ぶ特急「ラピート」用として製造された車両。何と言っても特徴的なのは外観形状で「レトロフューチャー」をコンセプトとしたデザインは一説によれば蒸気機関車と飛行機のイメージを近未来風にアレンジしたものだが、乗客からは「鉄人28号」と呼ばれているらしい。鉄道友の会「ブルーリボン賞」受賞車。 |
 |
■12000系(2011年) 南海本線用特急列車「サザン」の最新鋭車で10000系の老朽化に伴い登場した。車体は、8000系を踏襲したステンレス車体。また車内にはシャープ製イオン発生器「プラズマ・クラスター」を搭載し車内環境の向上を目指した。「サザン・プレミアム」の愛称で呼ばれる。 |
 |
■10000系(1985年) 南海本線用車両。大阪難波と和歌山港を結ぶ特急「サザン」に使用される。登場当初は白地にグリーンの塗色であったが1992年のCI導入に伴い、シルバー地にブルー・オレンジの塗色に変更された。また当初は2両編成であったが後に4両編成とされた。増備された中間車は窓形状が異なる。鉄道友の会「ローレル賞」受賞車。 |
 |
■31000系(1999年) 高野線用車両。特急「こうや」や「りんかん」に使用される。特急増発による増備のため4両編成1本のみの存在。外観は「りんかん」用11000系に類似しているが、橋本〜極楽橋間の、急曲線が続く山岳区間に乗り入れるため17m級車体となる。走行系機器は、閑散区間である山岳区間を走るため、またコスト削減のため廃車発生品を使用する。 |
 |
■30000系(1983年) 高野線用車両。橋本〜極楽橋間の山岳区間は急勾配・急曲線のため17m級車体と、山岳区間対応の性能となっているのが特徴。この幅広い性能を持つ事から「ズームカー」と呼ばれる。高野山観光客輸送の特急「こうや」の他、橋本までの通勤特急「りんかん」でも活躍する。 |
 |
■■8300系(2015年) インバウンド需要に対応する旅客案内設備の充実化を目的に導入された車両。車内にはLCDによる車内案内装置が搭載、また増備車ではスーツケースが邪魔にならないよう袖仕切り形状を改良、乗降扉横にラゲッジスペースが設けられた。従来、南海の車両は帝国車輌(現・総合車両製作所)により製造されていたが、この車両は近畿車輌が製造している。 |
 |
■8000系(2008年) 南海本線用車両。7000系の老朽化に伴う置き換え用として製造された。車体は1000系を踏襲しながらも製造元の東急車輛製造(現・総合車両製作所)が開発に携わった東日本旅客鉄道E231系の思想を取り入れている。現在は、通勤輸送のほか12000系と連結のうえ特急「サザン」としても活躍する。 |
 |
■■1000系(1992年) 南海本線と高野線両路線で共通運用が可能な車両として製造された車両。鋼体はステンレス車体で、グレー地にブルー・オレンジの新塗装が施された。最終増備である6次車のみはステンレス無塗装となる。1次車は車体幅が狭いタイプの車体であるが、2次車以降は拡幅車体となる。 |
 |
■9000系(1985年) 南海本線用車両。南海本線初のステンレス車両となる。旧1000系の老朽化に伴い高野線用8200系をベースに製造された。登場当時は、ステンレス車は高野線のみであり、誤乗防止のため当時の南海本線の塗色であったグリーンのストライプが施された。しかし後のCI導入に伴い、ブルーとオレンジのストライプに変更されている。 |
 |
■7100系(1969年) 南海本線用車両。架線電圧の1500V化により旧型車を大量に置換えるべく投入された。7000系をベースに乗降扉の両開き化、また側面窓を一段下降窓に変更した。普通列車から特急「サザン」自由席車までの幅広い運用に就く。しかし海岸付近を通る車両ゆえ、塩害による老朽化が進み、廃車が進む。 |
 |
■■2000系(1990年) 高野線用車両。橋本〜極楽橋間の山岳地帯を走行可能な仕様のいわゆる「ズームカー」。南海初のVVVFインバータ制御車両である。なお高野線のダイヤ見直しにより一部車両は運用余剰となったため、7000系置換え目的で南海本線へと転属された。また近年では汐見橋線でも活躍する。 |
 |
■8200系(1982年) 高野線用車両。1975年に、制御装置の試験のために製造された8000系(初代)の実績をもとに製造された車両。製造コストを考慮して界磁チョッパ制御とされた。前面形状は6200系をベースとしながらも若干の変更が施され、印象が異なる。車体長が20m級大型車であり山岳区間には入線できず、難波〜橋本間の通勤輸送に充当される。 |
 |
■6200系(1974年) 高野線用車両。6100系(現6300系)をベースとしながらも製造コストの低減が図られ、前面形状は切妻形状となった。車体長が20m級大型車であり山岳区間には入線できず、難波〜橋本間の通勤輸送に充当される。 |
 |
■6300系(1996年改造) 高野線用車両。1970年登場の6100系は南海本線用7100系に倣い6000系の改良版として登場した車両。乗降扉が両開き扉化と、側面窓が一段下降窓へと変更された。車体長が20m級大型車であり山岳区間には入線できず難波〜橋本間の通勤輸送に充当される。1996年より台車の交換と内装の変更が施され、6300系と改番された。 |
 |
■6000系(1962年) 高野線用車両。南海初のステンレス製車両である。また関西私鉄初のオールステンレス車両である。高野線の最古参であり、今や大手私鉄では数少なくなった片開き扉車である。車体長が20m級の大型車であり、山岳区間には入線できずなんば〜橋本間の通勤輸送に充当される。 |
 |
■9300系(2023年) 泉北線の最新鋭車両。南海8300系との共通設計車両であるが前面のアイボリー塗装や、木目調の車内にオリジナルを見出している。2023年度のグッドデザイン賞受賞車両。 |
 |
■7020系(2007年) 3000系の置き換え目的として登場した車両。7000系と比較して前面貫通路のプラグドア廃止など、設計変更によりコスト削減が図られている。対して室内には、泉北初の液晶ディスプレイによる車内案内装置が設置された。 |
 |
■7000系(1996年) 100系の置換えを目的として登場した車両。5000系に続いてアルミ車体となるが、前面は自動幌を備えたプラグドア式貫通扉という、通勤型ながら特急車両の様な設備を備えている。乗り入れ先の南海の車体限界が拡大された事により、この車両は泉北高速(当時)初の広幅車体として製造された。 |
 |
■5000系(1990年) 泉北高速(当時)初の自社設計車両。アルミ製車体にはアイボリー地にブルーのストライプが入る全面塗装となった。また泉北初のVVVFインバータ制御を搭載している。なお一部車両は南海標準色へと変更が進む。 |
 |
■3000系(1975年) 路線延伸に伴う輸送力増強のために製造された車両。南海6200系をベースとしているが、製造コスト低減のため、外板のみステンレスとし骨組は鋼製とした、セミステンレス車両として製造された。ただし後に製造された車両は骨組もステンレスとされている。 |
 |
■7000系(1963年〜2015年) 南海本線用車両。既に高野線ではステンレス車両の6000系が登場していたが、こちらはデザインこそ6000系を踏襲するものの、踏切の多い南海本線において踏切事故等での修繕のし易さから普通鋼が採用された。普通列車から特急「サザン」自由席車までと幅広い運用が行われたが、老朽化のため2015年をもって引退した。 |
 |
■22000系(1969年〜1998年) 高野線の山岳区間直通用車両「ズームカー」21001系の増結用車両として登場した。21001系と比較して丸みを帯びていない形状から「角ズーム」なる愛称を持つ。2024年、廃車となった編成が銚子電気鉄道へと譲渡、昭和の頃の懐かしい「ズームカー」カラーが復活した。※画像は銚子電気鉄道での撮影 |
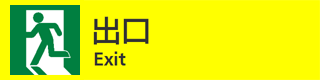 |
 |