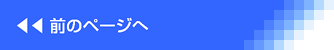 |
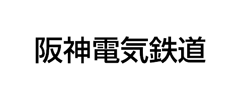 |
 |
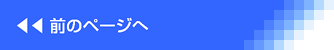 |
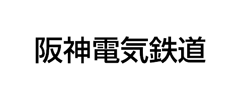 |
 |
 |
■1000系(2007年) 急行用最新鋭車両。なんば線および近鉄線への乗り入れ用として登場した。9000系以来のステンレス車体であるが、阪神の急行車用新塗色であるオレンジ色の塗装方法が乗降扉付近に変更された。また阪神車両では初めて、行先表示機がLED化された。6両編成の基本編成のほか、増結用として2両編成が在籍する。 |
 |
■9300系(2001年) 急行用車両。山陽電鉄姫路までの直通運転を考慮に入れ、一部ではあるが実に37年ぶりにクロスシートが復活した。また普通用車両である5500形に倣い、急行系車両としては初の新塗色を採用。しかしオレンジという塗色が「阪神にとってライバル球団の、読売ジャイアンツを連想させる」との理由で新塗色は評判があまりよろしくないとか。 |
 |
■9000系(1996年) 急行用車両。阪神大震災では、阪神の車両も甚大なる被害を受けたが、一刻も早く車両を確保するため、車両製造元の川崎重工で最も工期の早いステンレスを採用した。阪神では約20年ぶりのステンレス車両である。また急行用車両としては初のVVVFインバータ制御を採用した。なお現在は近鉄線直通への対応工事が施され、塗装もオレンジベースに変更された。 |
  |
■8000系(1984年) 急行用車両。従来車とは大幅に異なる前面形状で登場した。大きな前面窓に並んだライトというデザインは現在の車両に至るまで継承されている。阪神の急行車両の主力として活躍。登場当初は、阪神伝統の「赤胴車」塗装であったが、リニューアル工事と共に9300系と同等のオレンジベースに変更された。しかし2025年に入り赤胴車塗装が復活している。 |
 |
■8000系(第1編成・1984年) 急行用車両。8000系は、第1編成のみが従来の車両と大差ない外観となる。これは、武庫川線の路線延長に伴う車両転属で本線の車両数が不足したために、デザイン決定前に急遽増備されたためである。当初は両先頭車共この外観であったが、3両が阪神大震災で被災し廃車となったため、現在は後に新造された3両と連結されており、両先頭車で形状が異なっている。 |
 |
■5700系(2015年) 普通用車両。車体は1000系を基本とし、普通用車両としては半世紀ぶりにステンレス車体を採用。側面は、ドア周りにおもてなしの心と青い地球をイメージした青い丸が配される。車内は、全車両に優先席と車椅子・ベビーカースペースを設け、出入口側には、立客の腰当てにも使用できる大型の袖仕切が設置された。鉄道友の会「ブルーリボン賞」受賞車両。 |
 |
■5500系(1995年) 普通用車両。阪神大震災で被害を受けた車両を一刻も早く復旧させるべく導入された車両。震災復興で生まれ変わる阪神を表現すべく、車体色には新たに、上半分ライトブルー下半分ライトグレーという爽やかな塗色を採用した(現在は新塗装化)。制御装置は阪神初のVVVFインバータ制御を採用、また室内にも電光表示機を設置するなど、新時代の阪神を印象づけた。 |
 |
■5550系(2010年) 普通用車両。5500系のマイナーチェンジ車として登場した。機能面においては1000系に準ずる装備となる。従来、阪神の車両を製造していた武庫川車両が解散したため、車体は阪急系列のアルナ車両が製造、艤装は阪神車両メンテナンスにより行われた。奇しくも阪急阪神HD内の合作となる。1編成のみの存在で、ライトブルーの塗装も本系列のみ残された。 |
|
|
|
 |
■近畿日本鉄道・9820系(2001年) 近鉄奈良用8000系の老朽化に伴い登場した車両で「人に優しい地球に優しい」をコンセプトにした車両「シリーズ21」の奈良線バージョンとして登場した。阪神なんば線開業に伴い阪神と近鉄の直通運転が開始され、この車両は直通運転対応工事を施されており阪神三宮まで乗り入れる。 ※阪神の車両ではありませんが、乗り入れ車両として掲載しました。 |
 |
■近畿日本鉄道・1020系(1991年) 近鉄奈良線用車両。近鉄線標準軌区間の共通仕様となるVVVF制御車両である。ただし他形式が様々な線区で使用されているのに対し、この形式は何故か奈良線にしか配属されていない。阪神なんば線開業に伴い、阪神と近鉄の直通運転が開始され、この車両も阪神三宮まで乗り入れる。 ※阪神の車両ではありませんが、乗り入れ車両として掲載しました。 |
 |
■山陽電気鉄道・5000系(1986年) 神戸と姫路を結ぶ山陽電車の主力車両。鋼体はアルミ車体とし車内にはクロスシートを備える。制御装置は、界磁添加励磁制御という簡易省エネ制御を採用する。直通特急として姫路より阪神梅田まで乗り入れる。 ※阪神の車両ではありませんが、乗り入れ車両として掲載しました。 |
 |
■山陽電気鉄道・5030系(1997年) 山陽電車の主力車両である5000系は、阪神との直通運転を開始するのに伴い、車両不足を補うため再び製造されたがVVVF制御の採用や座席の転換クロスシート化など、変更が加えられた。そのため、この車両は5030系とも呼ばれる。直通特急として姫路より阪神梅田まで乗り入れる。 ※阪神の車両ではありませんが、乗り入れ車両として掲載しました。 |
 |
■2000系(1990年〜2011年) 急行用車両。1963年製造の7801形と、日本初の電機子チョッパ制御車両である1966年製造の7001形を、簡易省エネ制御である界磁添加励磁制御とし、また6両固定編成の改造を施した車両である。外観は従来車と大差ないが、室内は電光表示機が設置されるなど、新車と遜色のない改造が施された。老朽化のため2011年6月をもって引退した。 |
 |
■7861形・7961形(1966年〜2020年) 1967年の昇圧に伴う編成増強のため主力車両の4両編成化が発生したが、2両編成の車両が相対的に減少するため、2両編成車両を確保すべく1963年登場の7801形・7901形をベースに製造された車両。本線時代は混雑時の増結用として活躍したが、晩年は本線を離れ、武庫川線で活躍した。老朽化に伴い2020年をもって引退した。 |
 |
■5131形・5331形(1981年〜2019年) 普通用車両。非冷房車の淘汰に伴い登場した。5001形と同一の車体に、省エネ効果の高い電機子チョッパ制御装置を搭載した。制御器のメーカーにより百の位の数字が異なり、東芝製機器搭載車が5131形(東芝の「とお」で1)、三菱製機器搭載車が5331形(三菱の「みつ」で3)となる。部品調達が困難になったため抵抗制御車の5001形よりも先に引退した。 |
 |
■5001形(1977年〜2025年) 普通用車両。初代5001形の老朽化や非冷房車の淘汰に伴い登場した。製造当初は2両編成で方向幕も設けられていなかったが4両固定編成化工事の際に方向幕が設置された。また後年は車椅子スペースも設けられた。老朽化により2025年2月をもって引退した。 |
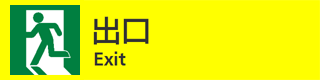 |
 |